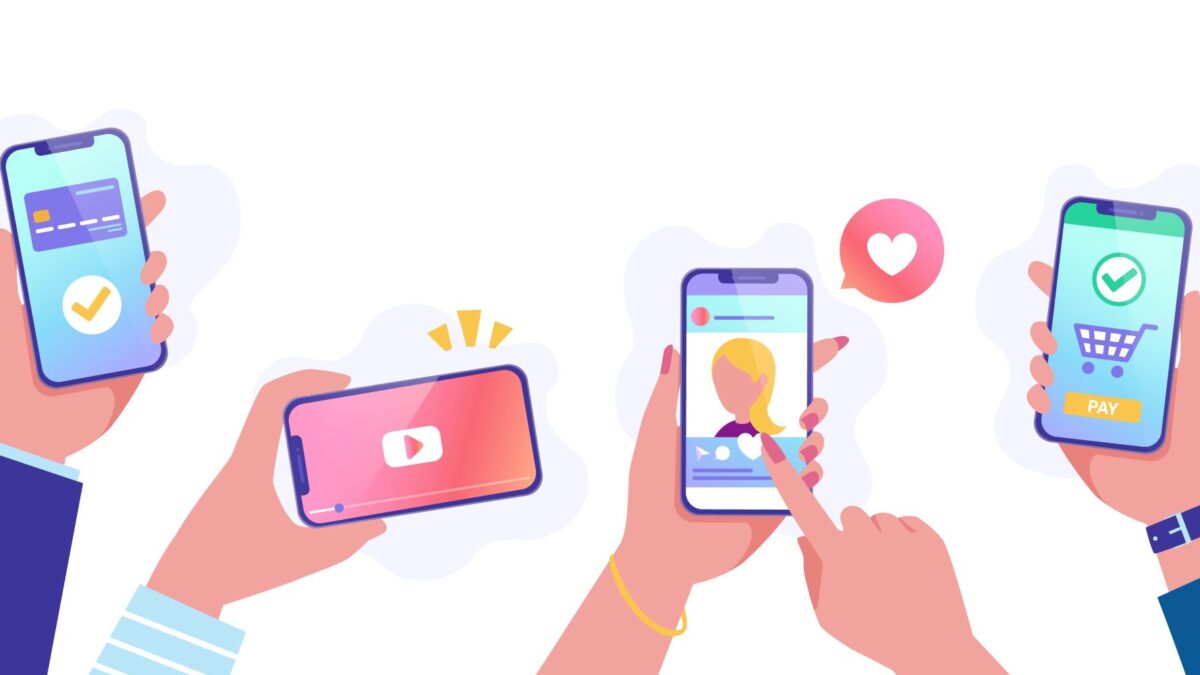2025年6月、私たちは新たなマーケティング戦略を立ち上げました。
それが「コーペラティブマーケティング」という、これまでになかった取り組みです。
簡単に言えば、「同じ業界内の事業者同士が手を取り合い、集客力を一緒に伸ばしていこう」というものです。
このアイデアの背景には、年々深刻化している「集客の格差」があります。
デジタル化による集客の二極化

インターネットがなかった頃は、地域にチラシを配ったり、看板を設置したり、口コミで集客が成り立っていました。
ところが現在は、ホームページ、SNS、広告運用、SEOなど、オンライン上の手段を駆使する必要があります。
こうした手段に習熟している企業は、検索上位に表示されることで安定的に問い合わせを獲得し、着実に成長を続けています。
一方で、情報発信が苦手だったり、運用に手が回らない事業者は、いくら素晴らしいサービスを提供していても、埋もれてしまうというのが現実です。
特に近年では、SNSやブログで反応を得ている方の多くが、「文章のセンス」や「継続力」といったスキルを持つ“発信の才能”を持った方々です。
そのため、表面的に真似しても、なかなか同じような結果は出せません。
力があるのに、目に留まる機会が少ない——。
そんな小規模事業者様のために、私たちは「連携による新しい集客の形」をご提案しています。
発想の転換:「ライバル」ではなく「仲間」へ

私たちの提唱する「コーペラティブマーケティング」は、同業者が互いに助け合うマーケティングの新しいモデルです。
一般的に同業者は“競争相手”と思われがちですが、エリアが異なれば利害はほとんど重なりません。
むしろ、業界の特性を理解し合えるからこそ、連携することで相乗効果を生むことができます。
この取り組みでは、同一エリア外の事業者同士が協力し合い、情報発信や集客において支援し合うことで、これまで一社では難しかったことを実現することを目指しています。
ここからは、現在進行中の「結婚相談所業界での実践例」をご紹介します。
取り組み1:共同運営による情報発信サイト
このプロジェクトの柱のひとつが、業界の枠を超えた共同運営型の情報サイトです。
たとえば下記のようなサイトが既に稼働しています:
▶ 婚活テラス
このサイトでは、複数の結婚相談所様が力を合わせ、婚活に関する知識やコラム、相談所の選び方などを発信。
サイトに訪れた読者を、各事業者様のページへとスムーズに誘導する導線を作っています。
一社で同じクオリティの情報サイトを維持するのは、記事作成、SEO対策、更新と非常に手間がかかります。
ですが、役割を分担すれば、少ない労力で質の高いコンテンツサイトが運営できるのです。
また、
- 都道府県別の特集ページでエリア毎に誘導
- 一括資料請求で複数社を検討してもらえる導線づくり
- 被リンクによるSEO評価の向上
といった追加効果も期待できます。
取り組み2:WEBやSNS上での相互サポート
もう一つの大きな柱は、デジタル領域での相互協力です。
たとえば、InstagramやX(旧Twitter)でお互いの投稿をフォローしたり、「いいね」やリポストを通じて反応を増やします。
SNSでは“最初の印象”がとても重要で、フォロワー数や反応が少ないと信頼性に欠けて見られてしまいます。
また、各事業者様のホームページに互いを紹介するページを設けることで、被リンク効果が得られ、SEOにも良い影響を与えます。
“1社では難しいけれど、複数社なら実現できる”施策を、実際に形にしていく取り組みです。
全員が参加できるわけではありません
このマーケティングモデルには参加条件があります。
商圏が重ならないよう、原則として1市区町村につき1社のみの参加とさせていただいています。
これまで全国20社以上の相談所様とミーティングを行ってきましたが、「同一地域内での連携は難しい」とのお声が多かったため、エリアの重複を避ける形でご参加いただいています。
この企画が生まれたきっかけ
この取り組みを思いついたきっかけは、ある結婚相談所の方との出会いでした。
非常に真摯な姿勢で会員様のことを第一に考え、日々全力でサポートされている方です。
私が結婚相談所を選ぶ立場だったら、間違いなくこの方のもとを訪ねたいと思うほど、信頼できる存在です。
しかし、知名度や資金力で勝る大手に比べて、集客という面ではどうしても不利な立場にあるのが現実でした。
このような“本当に良い事業者”が埋もれてしまうのを防ぎたい。
そういった想いが、このコーペラティブマーケティングの原点です。
他業種への展開も可能です
「同業者が手を組む」この取り組みは、結婚相談所に限らず、他の業界にも十分応用可能です。
医療、教育、美容、士業など、地域密着型の業種であれば、多くの分野に展開できると考えています。
同じような課題に悩まれている方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度ご相談ください。